伊那市で家庭ごみを正しく捨てるには?分別・収集・粗大(大型)ごみの出し方まとめ
伊那市の家庭ごみの出し方について、伊那市がインターネットというメディアを利用して私たちにわかりやすく家庭ごみ情報を提供されています。
伊那市ホームページの中から、家庭ごみやリサイクルのページを探し、伊那市の家庭ごみの出し方を紹介しておりますのでご活用いただければ幸いです。

平成25年4月1日から使用済み小型家電のリサイクルも始まり、パソコン、携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器、電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、これまでの法律では対象となっていなかったほぼすべての家電を対象として、リサイクルを進めていくことになりました。
お住まいの市町村の分別ルールに従い、正しくリサイクルしましょう。
スポンサード リンク
伊那市家庭ごみの出し方
伊那市のごみの出し方のページを見てみると、次のような項目で家庭ごみの分別・出し方が紹介されています。
伊那市のごみの出し方主な品目の紹介
■資源ゴミ 伊那市のゴミ・リサイクルページの主な内容紹介
「燃やせるごみ」の出し方
生ごみ、資源化できない紙類、布類、木製の物、プラスチック製品、ビニール製品、ゴム製品、アルミ箔製品など
「燃やせないごみ」の出し方
金属、陶磁器、ガラス類など
「有害ごみ」の出し方
「粗大ごみ」の出し方
お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 生活環境課 環境衛生係
電話:0265-78-4111(内線2214 2215 2213)
ファクス:0265-74-1260
直接搬入するもの
粗大ごみ・大型可燃ごみ
指定ごみ袋に入らない大きなものは処理施設へ直接持ち込んでください。
粗大ごみ
粗大ごみは「クリーンセンター八乙女」へ
注意:タンス等は壊さずにそのまま搬入してください。
クリーンセンター八乙女
箕輪町大字中箕輪3819番地
TEL79-8773
料金:20kgまで400円、20kgを超過分・10kg当たり200円(一般家庭)
大型可燃ごみ
大型可燃ごみは「上伊那クリーンセンター」へ
上伊那クリーンセンター
伊那市富県3790番地
TEL98-8337
料金:20kgまで400円、20kgを超過分・10kg当たり200円(一般家庭)
布団、畳(1日10枚まで)、カーペット、剪定枝 など
※指定ごみ袋に入らないプラスチック製品は“粗大ごみ”になります。
注意
剪定枝は太さ10cm以下で長さ50cm以下に切断してください。
木製の板を持ち込む場合は、太さ10cm、長さ・幅50cm以下にしてください。
「その他のごみ」の出し方
「資源プラスチック(プラスチック製容器包装)」

「古紙類(段ボール、新聞紙・広告・ちらし、雑誌・古本、その他の紙」の出し方
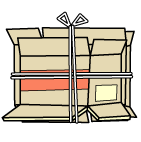

「牛乳パック」の出し方

収集日当日の朝、午前8時までに各地区の決められた資源物ステーションに出してください。
「廃食用油」の出し方
収集日は隔月です。
「缶類(飲料缶、缶詰の缶、粉ミルク等の缶、海苔やお菓子の缶など)」の出し方

 スチール缶、アルミ缶の2種類に分けて、収集ステーションに用意された専用回収容器に入れてください。
スチール缶、アルミ缶の2種類に分けて、収集ステーションに用意された専用回収容器に入れてください。
「びん類(飲料、食料品、調味料など飲食が可能な物が入っていたびん類)」の出し方
「ペットボトル(飲料水や各種お茶、乳飲料、酒類、醤油のペットボトルなど」の出し方

プラスチックボトルとペットボトルは違う物です。マークを確認していただき、プラスチックボトルは資源プラスチックとして出してください。
■詳しくは…伊那市ごみ・環境のページをご覧ください。
スポンサード リンク
![]()
伊那市家庭ごみ関連情報
伊那市の粗大ごみ、布団、プリンター、ソファー、家具処分方法
- 伊那市パソコン廃棄方法
- 伊那市冷蔵庫処分方法
- 伊那市洗濯機処分方法
- 伊那市テレビ処分方法
- 伊那市エアコン処分方法
【伊那市で処理できないごみ】
伊那市のパソコン、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコン処分方法
小型家電リサイクル法知っていますか?
使用済み小型家電は、都市にある鉱山という意味で「都市鉱山」といわれるくらい、鉄、アルミ、銅、貴金属、レアメタルといった有用な金属がたくさん含まれています。小型家電はリサイクルが可能な貴重な資源なのです。
使用済みになった家電製品のリサイクルは、これまで、テレビやエアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機といった「家電リサイクル法」に定められた4品目でした。
平成25年4月からは「小型家電リサイクル法」により、パソコン、携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器、電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、これまでの法律で対象となっていなかったほぼすべての家電を対象として、リサイクルを進めていくことになりました。
家庭ごみの出し方は住んでいる地域のルールに従いましょう
燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミ、粗大ゴミなどに分けることがゴミ分別の基本ですが、この分別の仕方は地域によって違うのが現状です。これは、各自治体のゴミ処理方法や施設の違いによるものですから、皆さんの住んでいる地域のルールに従って分別をする必要があります。
間違った分別をしないために、地域のルールをチェックしておきましょう。
